いろいろな珈琲の飲み方がありますが、今回は口当たりも軽く、アメリカンコーヒーについてのお話しをしたいと思います。
『アメリカ』と『コーヒー』と聞いて、人によってはダイナー(軽食店)でのカウンター越し、ウェイターから勧められるポット入りのコーヒーを思い浮かべるかも知れません。
思えば、今や世界的企業であるスターバックスも、シアトルからの企業ですが、では元々のアメリカと珈琲との関わりはどの様な形だったのかも気になる所です。
今でも「新大陸」と呼ばれ続けているだけあって、元はヨーロッパ、特に独立前はイギリスからの植民地であったのがアメリカです。
喫茶文化を見ても、とうぜん紅茶の国からの支配下にあった事が分かります。
印税や鉄鋼業をはじめ、お茶にも課税がなされていました。
そこから、イギリスからの紅茶が海に放り込まれる、有名な『ボストン茶会事件 (Boston Tea Party)』が起こってからが、アメリカ独立の流れと、喫茶珈琲への転向の始まりと言えるでしょう。
1773年に起こりました。
ちなみに、名称にTea Partyとありますが、「ちょっとしたお茶会」と言った皮肉な意味合いと、「ひと騒動」と言う少々過激なニュアンスもあります。
広く知られている「アメリカンコーヒー」の飲み方は、個人的な印象もありますが、本国の方々はそれほどこの飲み方を意識している様には思えなく、むしろ珈琲が広まった時、そして現代に定着した時のスタイルや背景に拠るものに感じます。
一般的には、浅く炒った豆を多めのお湯で落としたもので、サクサク飲める飲み方なのがアメリカンコーヒー。
浅く炒った豆を用いた理由は、先にお話しした茶会事件の後、他のヨーロッパから珈琲豆を輸入した時、成分量や等級では無く、キロ数当たりで計算をしていたので、焙煎によって飛んでしまう水分由来の目減りが少ない浅炒りが、好んで取り引きされていたからです。
多めのお湯、ちょっと聞こえが悪いかも知れませんが薄め、あるいは「軽めの抽出」の理由は2つあると考えていて、近代経済、特にオフィスでのスタイルになってからの経済活動の原動力となる為に、胃に負担も少なく、多めに飲むことができる形態が好まれていたのではないかという考え。
もうひとつは第二次世界大戦の終盤、さすがのアメリカも物資の不足による「嵩増し」をせざるを得なかった、といった世界情勢的な背景も、アメリカンコーヒーの出自の由来なのではないかというものです。
さいごに余談となりますが、占星術や魔術を請け負う職能集団、いわゆる『魔女』の間でのお茶会(Tea ceremony)の後には、カップの底に残った茶葉の位置や形から、占いの材料としていたのですが、手元の資料を見ると、珈琲でも同じことができる様です。
抽出の方法でも、残渣の具合が変わりそうですが、どうやら新大陸でも魔術の世界は存在している様です。
只の液体以上の意味づけを薄く感じつつ、今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。

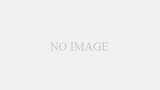
コメント