「コーヒーの豆とは」の項で、コーヒーの豆とはアカネ科の「コーヒーノキ」という木につく実の中にある「種」である、ということを解説しました。
この項では、「コーヒーノキ」について少し、ざっくりと解説してきます。
このアカネ科の植物は元々、常緑の熱帯性低木で学名をコフィラ・アラビカといいます。
種を蒔いてから実を付けるまで3~5年を必要とし、また、収穫可能な期間は約20年と言われています。
コーヒーノキのほとんどは5弁の白い花をつけ、ジャスミンを思わせる香りを放ち、葉は栗の葉に似ていて厚く、実は枝にたわわに着生します。
つきはじめは緑色の果実が徐々に赤みを増していき、成熟すると真っ赤になります。
「コーヒーの豆とは」の項目でも触れましたが、真っ赤に完熟した果実がサクランボの実に似ていることから「コーヒーチェリー」と呼ばれています。
野生のコーヒーノキは5m以上、種類によっては8m以上にも生育しますが、コーヒー農園では栽培・生産管理がしやすいようにせん定されています。
(詳しくは「コーヒーの栽培から収穫まで」で解説しています。)
植物学ではコーヒーノキは、アカネ科・コヒア属・ユーコフィア節に分類されています。アカネ科の植物には有用植物が数多くあります。例えば、薬用としてマラリアの特効薬キニーネとなるキナノキ、また茜染などの染料として使われるアカネやセイヨウアカネ、クチナシなどよく知られる種類です。
コヒア属には50から60とも言われる「種」が存在しています。コーヒーノキはその種子に含まれるアルカロイドのカフェインにより、古くから薬用として用いられ、さらに14~15世紀以後は独特な飲用植物として位置づけられてきたものです。
その栽培の歴史は500年を超え、現在では各生産国の栽培者や、研究者が研究開発している品種は数百種にものぼると、思われています。
しかし現実には、世界中の産地で実用的に栽培されているコーヒーノキは「アラビカ種」
「ロブスタ種」「リベリカ種」の三種で、コーヒーノキの「三大原種」と呼ばれ、植物学的にはもちろんですが、コーヒーの品質、流通の最も基本的な分類になっています。
(詳しくは「コーヒーの品種」で解説しています。)
コーヒーノキの栽培は病害と霜害のへの対策の歴史でもあり、栽培に適する環境をさらに求め、今日のように世界各地で栽培されるようになるまで、厳しい道のりがありました。
コーヒーノキの病気は、現在知られているだけでも350種を超え、さらに次から次へと新しい病気も発見されています。
その中でも、最も大きな被害を及ぼしたのが、さび病菌「ヘミレア」です。
この菌はコーヒーノキの葉の裏側に付着し、葉肉内に菌糸を伸ばして養分を奪って植物を枯死させてしまいます。
初めは1~2㎜くらいのほんの小さな淡黄色の斑点ですが、この斑点におおよそ100万個もの胞子がが巣くい、どんどん増殖を始めます。その後、斑点の色は次第に濃くなり、それにつれて葉の緑色は色褪せていき、大きさも委縮していきます。光合成機能も低下し、2~3年後には木そのものが枯れ果ててしまいます。
1861年に北東アフリカのウガンダ、エチオピアで発生したさび病は猛威をふるい、アジア・アフリカの各地域で栽培されたアラビカ種を壊滅状態に追い込みました。特にスリランカは悲惨で、1869年にコーヒー農園は全滅しました。そのことによってスリランカはコーヒー栽培を放棄し紅茶の栽培に切り替わりました。
また1876年にインドネシアのジャワ、スマトラにもさび病が発生し、当時栽培されていたアラビカ種の農園に壊滅的打撃を与えました。
しかし、アメリカ大陸はさび病の発生をまぬがれました。このことが、ブラジルが世界最大のコーヒー生産国になった事のきっかけになったと言われています。
その後1970年についにブラジル、バイヤ州の農園でさび病が発生し、また中米諸国にも広がっていました。その為、世界のコーヒーの取引市場は大混乱をおこしました。
さび病から逃れるため、耕地をより冷涼で乾燥した高原などへ移動させたり、さび病に対して抵抗力を認められるロブスタ種やリベリカ種に注目し栽培品種を切り替える手段をとる一方、さらに強い抵抗力を持つ品種の研究が世界各国で進められています。
また、品種そのものの研究の他に、さび病に特効的な働する農薬の研究も進めらています。
耕地で栽培されるコーヒーにとって、もっとも怖い災害は霜害です。たった一夜に降りた霜のために、栽培地域全域が壊滅的な大打撃を受けることさえあります。過去、コーヒーの最大の生産国のブラジルは霜害によって大きな痛手を被ってきました。南半球のブラジルでは7月は真冬に当たりますが、この時期の南極からの寒波とアンデス山脈からの寒気にコーヒー生産地帯の高原が襲われ、急激に気温が下がり、さらに強風がおさまった晴天の夜明けに霜がコーヒー農園に降り、コーヒーの葉や枝が冷凍状になってしまいます。そしてその翌日、今度は強い日差しを受け冷凍状態の葉の水分が暖められることになり、緑の葉が茶褐色となって落葉しコーヒーノキそのものが枯死してしまいました。
1975年の霜害では20億本のコーヒーノキの内、15億本が被害を受け、生産が半減以下となってしまいました。
栽培種の歴史を見てみると、かつて「アラビカ種」が世界の栽培地が席巻していきましたが、1870年頃を境に「リベリカ種」が加わって来ます。リベリカ種は高温皇室に強く、またさび病に対する抵抗性もあったことから、次第に栽培範囲を広げていったのでした。
そして、1898年に新しい耐病種の「ロブスタ種」が発見され、さび病に悩む地域を中心に栽培されて行きました。

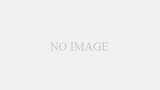
コメント