今回は珈琲がここまで愛されるようになった理由の1つになったカフェインについてお話しをしたいと思います。
珈琲の抽出物からの発見から、その名がついた事は容易に想像がつく事でしょう。
英語でのスペルは”caffeine”です。
医療の世界では中枢神経に対する刺激薬という認識がされています。
中枢神経とは、脳や脊髄と言った、体の中心にあって、感覚や主な情報を取りまとめる部分と捉えてください。
広く知られている様に、おもな作用に覚醒があります。
眠気覚ましに珈琲を飲む、なんて経験は誰しも経験があるのではないでしょうか。
ほかにも心臓の働きを上げる強心作用、解熱鎮痛作用、皮下脂肪燃焼(嬉しい側面でしょうか)、利尿作用、胃酸量の増加、等々が有ります。
代表的なものを列挙してみましたが、これらの作用を利用した商品は意外と多くあります。
例えば痛みや熱に対して、そして服用した後の使用感を目的として絵総合感冒薬にも、カフェインが含まれる商品もあります。
食事に絡めたお話しをすると、いわゆる「食後の珈琲」の文化を持つ西欧は、炭水化物―タンパク質傾向のアジア的食習慣に対して、タンパク質―脂質寄りの食事内容を持つので、消化の助けになる珈琲の消化液分泌促進の作用も魅力的だったのではないかと察しが付きますね。
『コーヒー&シガレッツ』というモノクロ映画が、2003年にありました。
11作品がその中に収録されているいわゆるオムニバス形式の作品だったかと記憶しています。
どの作品でも基本的に、テーブルを挟んで珈琲やタバコに手を付けながら取り留めのない会話を続けてゆく、といった、説明事態は簡単な映画なのですが、個人的にとてもお勧めしたい作品の1つです。
大抵のシーンは何となく気まずい雰囲気の二人。でもそこには珈琲とタバコが取り持ってくれる、という微妙な間の繋ぎが、モノクロの視覚と相まって嗜好品の一つの側面を見せてくれる良作に思います。
薬理学的なお話しもしますと、このカフェインという物質はCYP1A2という名前の消化酵素で分解されるものです。「シップ・ワンエーツー」と読みます。
ご想像の通り、その消化酵素が多ければ、カフェインは速やかに体から代謝されますし、反対に阻害されて代謝されずにいると普通より長く効き目が残ることになります。
薬理の世界では、それぞれ消化酵素には阻害剤や誘導剤という存在がいて、このCYP1A2のお話しでは誘導剤の1つにタバコがあります。
端的な解釈をすると、タバコでその消化酵素が誘導されて数が増える事に因って、カフェインの作用が穏やかになるのではないかと考えられるのですが、そこから先は個々人の効き目の具合となってしまうので、この話しは参考程度です。
思えば『コーヒー&シガレッツ』も、全体的に穏やかで一種の倦怠感や間を感じさせる様な作品であったので、エナジードリンクの様な激しさとはまた違った、珈琲に拠る会話の一押し一押しを見せてくれました。
反対に阻害剤についてのお話しも付け加えておきますと、抗生物質や抗鬱剤、高血圧・狭心症の薬の、飽くまで一種が、CYP1A2の阻害剤となっているので、もしこのような症状に対して服薬をしていて、寝れなさすぎて珈琲から遠ざかっている方が居れば、医療者と相談する価値はあると思います。
服薬の見直しの道もあるでしょうし、最近は液体二酸化炭素抽出法なる技術で、味わいがほとんど損なわれないと振れ込みの珈琲も出て来たようです。
今回は喫茶的な意味合いから離れた、少し科学的なお話しになった所で、お終いにしたいと思います。

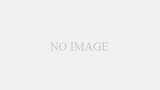
コメント